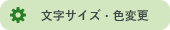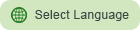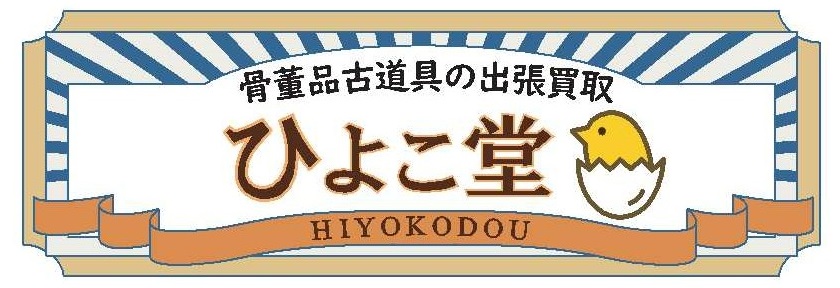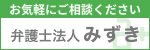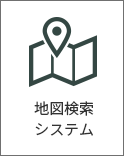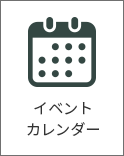国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費などを支払うための大切な財源となります。加入されている皆さんが、病気やけがをしたとき安心して治療が受けられるように、加入者全員がお金を出し合って助け合う制度です。
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
- 税金を納める方(納税義務者)
- 国民健康保険税の賦課
- 国民健康保険税額の決め方(令和7年度)
- 国民健康保険税の軽減
- 未就学児の均等割額軽減
- 産前産後期間における国民健康保険税の減額
- 国民健康保険税の内訳
- 国民健康保険税の納め方
- 年金からの天引き(特別徴収)と口座振替の選択ができます
- 国民健康保険税額の試算
- 国民健康保険税の納付に困ったとき
- 国民健康保険税に関するお問い合わせ先
税金を納める方(納税義務者)
その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主に送付します。世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主として世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税の賦課
国民健康保険税は、届け出た日からではなく、本来、加入すべき日から計算されます。年度の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月分までを月割り計算します。
国民健康保険税額の決め方(令和7年度)
以下の医療保険分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分についてそれぞれ計算し、その合計額が1年間の保険税額となります。
|
区分 |
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 (賦課限度額65万円) |
加入者全員の基準総所得額(注1)×6.3% |
加入者の人数 |
一世帯につき |
| 後期高齢者支援金等分 (賦課限度額24万円) |
加入者全員の基準総所得額(注1)×2.2% |
加入者の人数 |
一世帯につき |
| 介護納付金分 (賦課限度額17万円) |
40歳以上65歳未満の方の基準総所得額 (注1)×1.9% |
40歳以上65歳未満の方の人数 |
一世帯につき |
(注1)基準総所得額とは、次の計算式で算出される額のことです。
基準総所得額=前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)
総所得金額等には、給与・事業(農業・営業)・雑・譲渡・不動産・配当・利子・一時所得等のほか、山林所得金額、土地・建物等に係る長期譲渡・短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額が含まれます。
所得割額・均等割額・平等割額の合計額が、医療保険分で65万円、後期高齢者支援金等分で24万円、介護納付金分で17万円を超えるときはそれぞれ65万円、24万円、17万円が年間の保険税額です。(賦課限度額)
「後期高齢者支援金等分」とは、「後期高齢者支援金」に、後期高齢者医療制度の運営に関わる事務執行に必要な費用として「後期高齢者関係事務費拠出金」を加えたものです。
国民健康保険税の軽減
世帯の所得(国民健康保険加入者全員の所得の合計)が一定の金額以下の場合に、保険税の軽減措置があります。
下記の判定基準により、均等割額・平等割額が7・5・2割軽減されます。
ただし、国民健康保険加入者全員が所得の申告をされている、もしくは扶養等になっている世帯が対象です。擬制世帯主の所得も含めて判定します。
|
軽減割合 |
軽減判定基準 |
|---|---|
|
7割軽減 |
世帯の所得の合計額≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
|
5割軽減 |
世帯の所得の合計額≦430,000円+(305,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
|
2割軽減 |
世帯の所得の合計額≦430,000円+(560,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
※65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で判定します。
※「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者が対象となります。
未就学児の均等割額軽減
令和4年度分以降の国民健康保険税について国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。世帯所得に応じた軽減措置を受ける未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。
| 所得による軽減区分 | 未就学児の軽減前均等割額 | 未就学児の軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 軽減なし | 38,400円 (医療分28,800円) (後期分9,600円) |
19,200円 (医療分14,400円) (後期分4,800円) |
| 7割軽減の世帯 | 11,520円 (医療分8,640円) (後期分2,880円) |
5,760円 (医療分4,320円) (後期分1,440円) |
| 5割軽減の世帯 | 19,200円 (医療分14,400円) (後期分4,800円) |
9,600円 (医療分7,200円) (後期分2,400円) |
| 2割軽減の世帯 | 30,720円 (医療分23,040円) (後期分7,680円) |
15,360円 (医療分11,520円) (後期分3,840円) |
※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
産前産後期間における国民健康保険税の減額
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和6年1月より、下野市国民健康保険に加入している出産予定の方、あるいは出産された方について、産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
この減額を受けるためには、国民健康保険税の納税義務者(世帯主)からの届け出が必要です。
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の減額方法
-
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※減額期間中に、社会保険等の期間がある場合は、本市の国民健康保険の加入月数に応じて、部分的に保険税を減額します。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。 - 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
- 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
- 保険税が減額された場合、 納め過ぎになった保険税は還付されます。
届け出に必要な書類
- 産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(税務課窓口にて配付 または 以下よりタウンロードできます)
![]() 産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(pdf 482 KB)
産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(pdf 482 KB)
![]() 【記入例】産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(pdf 520 KB)
【記入例】産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(pdf 520 KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)
- 母子健康手帳など、出産予定日または出産日や、単胎妊娠または多胎妊娠が確認できる書類
- 出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類
- 別世帯の方が届け出る場合は、減額対象被保険者の納税義務者(世帯主)からの委任状が必要となります。
届出方法
- 窓口提出の場合:下野市役所 1階 税務課市民税グループへ届け出てください。
- 郵送による場合:〒329-0492 下野市笹原26番地 下野市役所 税務課 市民税グループ あてに郵送してください。なお、郵送の場合は、必要書類(本人確認書類や母子健康手帳など)は、原本ではなく「写し」を添付してください。
国民健康保険税の内訳
納付する保険税は年齢によって異なります。
| 年齢区分 | 納付する保険税の種類 | 介護納付金分の取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|
| 40歳未満の方 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | - | 介護納付金分の負担はありません。 |
| 40歳以上65歳未満の方 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | 第2号被保険者として、国民健康保険税に介護納付金分が加算されます。 |
| 65歳以上75歳未満の方 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | - | 第1号被保険者として、国民健康保険税とは別に介護保険料を納付していただきます。 |
※年度の途中に40歳になったときは、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)分から介護納付金分がかかります。
※年度の途中で65歳になったときは、65歳になる前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護納付金分を年度末までの納期に按分して国民健康保険税として納めます。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納め方は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と年金からの天引き(特別徴収)の2通りがあります。
納付書または口座振替による納付(普通徴収)の場合
1年間の保険税を7月(第1期)から翌年2月(第8期)の8回に分けて、納付書または口座振替でご納付いただきます(全期前納の方は7月に1回のみ納付)。
年度当初の納付書は、毎年7月15日ごろの発送です。
| 納付する月 | 普通徴収で納付(年8回) |
|---|---|
| 4月 | なし |
| 5月 | なし |
|
6月 |
なし |
|
7月 |
1期 |
|
8月 |
2期 |
|
9月 |
3期 |
|
10月 |
4期 |
|
11月 |
5期 |
| 12月 | 6期 |
| 1月 | 7期 |
| 2月 | 8期 |
| 3月 | なし |
年金からの天引き(特別徴収)の場合
医療制度改革に伴う地方税法の改正により、平成20年10月から年金からの天引き(特別徴収)がはじまりました。対象となる方は、下記の条件のすべてを満たす世帯主の方です。
- 国民健康保険に加入している世帯主
- 国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までの世帯の世帯主
- 特別徴収対象年金額が年額18万円以上であり、かつ介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金天引きの対象となる年金額の2分の1を超えない世帯主
1年間の保険税を年金から6回(年金支給月の偶数月)に分けて納付いただきます。
| 納付する月 | 年金天引きで納付(年6回) |
|---|---|
| 4月 | 1回目 |
| 5月 | なし |
|
6月 |
2回目 |
|
7月 |
なし |
|
8月 |
3回目 |
|
9月 |
なし |
|
10月 |
4回目 |
|
11月 |
なし |
| 12月 | 5回目 |
| 1月 | なし |
| 2月 | 6回目 |
| 3月 | なし |
※年金天引きの開始時期によっては、上記と回数が異なったり、納付書または口座振替による納付(普通徴収)との併用の場合もあります。
※介護保険料・国民健康保険税と年金額の比較判定は毎年7月に行います。判定結果によっては、普通徴収による納付に変更になる場合があります。
「介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金天引き(特別徴収)の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと」の判定方法
介護保険料と国民健康保険税が年金天引きに該当するかしないかの判定は、「介護保険料と国民健康保険税の合算額が対象となる年金の2分の1を超えないこと」が条件の一つになっています。この条件は次のとおり判定します。
《例》
国民健康保険税年税額209,200円
[税額内訳]
4月年金天引き:43,200円
6月年金天引き:43,200円
8月年金天引き:43,200円
10月年金天引き:26,600円
12月年金天引き:26,500円
2月年金天引き:26,500円
1回あたりの老齢基礎年金額の2分の1→62,791円
(1年あたりの老齢基礎年金額753,494円÷6回[年金支給回数]×0.5)
10月に年金天引きされる介護保険料→12,300円
2分の1を超えないことの判定
62,791円(1回あたりの老齢基礎年金額の2分の1)>38,900円(介護保険料[10月年金天引き]12,300円+国民健康保険税[10月年金天引き]26,600円)
→介護保険料と国民健康保険税の合算額が対象となる年金の2分の1を超えない。→年金天引き(特別徴収)の対象
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替の選択ができます
納付方法が、年金からの天引き(特別徴収)の方でも、ご本人の申し出により「年金からの天引き(特別徴収)」から「口座振替」に変更することが可能です。
希望する方は、「納付方法変更申出書」(税務課へ提出)、「口座振替依頼書」(金融機関へ提出)が必要となりますので、税務課市民税グループへお問い合わせください。
国民健康保険税額の試算
国民健康保険税額をEXCELにて試算することができます。
![]() 国民健康保険税試算表(令和7年度版)(xls 88 KB)
国民健康保険税試算表(令和7年度版)(xls 88 KB)
※試算結果は概算額です。税額の軽減措置等は含まれておりませんので、正式な税額は納税通知書でご確認ください。
国民健康保険税の納付に困ったとき
事情により保険税の納付が困難な場合には、税務課収納グループへお早めにご相談ください。
国民健康保険税に関するお問い合わせ先
- 課税に関すること
市民税グループ 電話番号:0285-32-8891 - 納付に関すること
収納グループ 電話番号:0285-32-8893