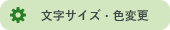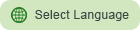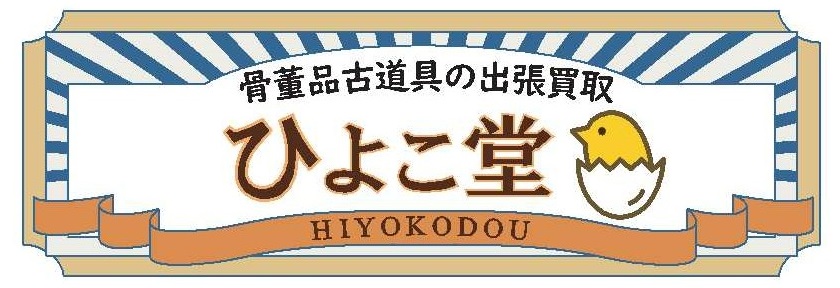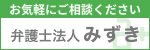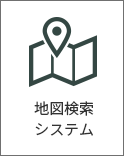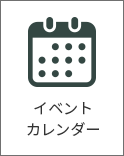令和6年度 市長コラム
令和7年3月「石橋第2配水区内の水道水について」
1月20日に採水した石橋第2配水区内の水道水から、国の暫定目標値1リットルあたり50ナノグラムを超える52ナノグラムの有機フッ素化合物(PFAS)が検出されました。
このPFASについては、国などの情報によれば、目標値を超えても直ちに健康被害を及ぼすものではないとされております。
しかしながら私は、市民の皆さまにこれからも安心して水道水をご利用いただけるよう、水質管理の強化、安定した水源の確保等に必要なあらゆる施策を早急に実施してまいる考えです。
あわせて、原因の究明などの市単独では難しい対策の実施や、市の取り組みに対する財政支援等に関する緊急要望書を、国並びに栃木県に提出したところであります。
また、本件の対応にあたり、ご協力をいただいております多くの方々に心より感謝申し上げます。
石橋第2配水区内にお住まいの皆さまにおかれましては、不安な日々をお過ごしのことと思います。市といたしましては、職員一丸となって、一刻も早く皆さまに安心して水道水をご利用いただけますよう尽力するとともに、引き続き必要な情報の迅速な発信に努めてまいりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和7年2月「指定ごみ袋制度の導入」
下野市のごみ処理を行っている小山広域保健衛生組合では、燃やすごみの減量化を目的に昨年10月より指定ごみ袋制度を導入し、今年4月から完全実施となります。
この指定ごみ袋には「もやすしかないごみ」と表記されていますが、この言葉に市民の皆さまは、少し戸惑いがあるかもしれません。これまで、燃やすごみの中には紙類やプラ製容器包装などの資源物が約20%も含まれていたことから、更なる分別を徹底したうえで、最終的に「燃やすことがやむをえないごみ」であることを皆さまにご理解いただくことが目的です。
ごみの分別にあたっては、市民の皆さまにはご負担をおかけいたしますが、「もやすしかないごみ」の袋を利用する際、処分しようとしているものが再生可能な資源であるか、「ごみの分別ルール」をあらためてご確認いただき、ごみの減量と限りある資源の循環の促進のために、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
令和7年1月「未来にむけた魅力あるまちづくり」
新年あけましておめでとうございます。謹んで、新年のごあいさつを申し上げます。
旧年中は市政運営に深いご理解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。数年にわたり日常生活や社会活動を脅かした新型コロナウイルス感染症の蔓延も落ち着きを見せ、地域での市民交流活動が復活されてきたことは、大変喜ばしい限りです。
そのような困難を乗り越えたという貴重な経験を糧に、また、市長就任以来心がけている、できるだけ市民の皆さまのご意見を直接お聴きすること、市民の皆さまと同じ目線でまちづくりに取り組むことを大切にしながら、「住みよさ」という本市の魅力をより一層高めるべく、引き続き邁進いたします。
昨年は、市の歴史的特性を活かして「東の飛鳥」ブランドを用いたシティプロモーションを本格的に開始するとともに、念願だった自治医科大学との連携協定を締結するなど、大変意義深い一年でした。
今年も、「ともに築き未来へつなぐ幸せ実感都市」という市の将来像の実現に向け、子育て環境の充実や、誰もが幸せに暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みを加速するとともに、(仮称)下野スマートIC整備や、「都市核」と位置づける市役所周辺地域の整備に向けた取組みを進めるなどして、引き続き「人や企業に選ばれるまちづくり」を推進してまいります。
来る4月にはドイツのディーツヘルツタールとの姉妹都市締結から50年、また令和8年1月10日には、下野市が誕生して20年となります。
合併以前の3町の時代から、今日「住みよさランキング県内1位」と評されるまでに至る歴史を
紡いでこられた先人の皆さまのご尽力に敬意を表すとともに、この機を更なる飛躍の節目ととらえ、現在策定を進めている「第3次下野市総合計画」に、より高い目標を掲げ、積極的にチャレンジしてまいりたいと考えています。
結びに、本年が市民の皆さまにとって、幸多く実りある輝かしい年となりますよう、心からご祈念申し上げます。
令和6年12月「今年を振り返って」
12月を迎え、今年1年の市内の出来事を振り返ってみますと、石橋高等学校野球部の夏の甲子園初出場と初勝利が、特に印象深いものでした。選手の皆さんの活躍はもちろんですが、まち全体を巻き込んで大きな旋風を起こしてしまうほどの若い力の素晴らしさに、私も心が熱くなりました。
さて、市の施策に目を向けてみますと、皆さまから最も反響の大きかったことは、自治医科大学との包括連携協定締結です。この協定の締結は、両者の連携をより強固にするものであり、下野市の「医療のまち」としての魅力がより一層向上する契機となったものと確信しています。
私は、下野市が「医療のまち」として発展していくために最も重要なことは「市民の皆さまがいつでも安心して医療機関を受診することができる環境づくり」であると考えています。実現には課題もありますが、まずは医療の現場の状況を把握しつつ、調査研究を行ってまいります。
その他にも、下野市の住みよさにさらに磨きをかけるべく、今後もさまざまな施策に取り組んでまいりますので、変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。
年の瀬も押し迫ってまいりましたが、皆さまにおかれましては、良い年がお迎えできますようお過ごしいただけましたら幸いです。
令和6年11月「市長のいきいきタウントーク」
先月、市内3つの会場で市政懇談会(市長のいきいきタウントーク)を開催しました。市民の皆さまと顔を合わせて意見交換や対話ができ、大変有意義な時間となりました。ありがとうございました。
参加された方々からは、道路などのインフラ、自治会活動、教育、子育て支援、市の行財政など、幅広くご意見やご質問をいただきました。
皆さまからいただいたお声を真摯に受け止め、課題の改善に向けて精一杯取り組んでまいります。これからも、さまざまな機会で積極的にご意見をいただけましたら幸いです。
ところで、近年、選挙の投票率低下が問題視されています。投票率向上を目指し、広報活動に力を入れることも大事かもしれませんが、何より大切なことは、市民の皆さまに政治や行政に関心を持っていただくことだと私は考えております。
そのためにも、今後もさまざまな世代の方々との対話を大切にし、一人でも多くの方に政治や行政に関心を持っていただけるよう、また、そうした方々が意見を発信しやすくなるよう、少しでも政治へ参加していただけるような環境づくりに努めていけたらと思います。
皆さまの思いを大切に、下野市がさらに住みよく、そして未来に向けて魅力と活力があふれるまちとなるよう、今後も引き続き、まちづくりを進めてまいります。
令和6年10月「災害への備え」
今年も全国各地で局地的な大雨や台風に見舞われ、改めて災害はいつ起こるかわからないこと、普段からの備えの重要性を痛感したところです。
市では、8月25日に総合防災訓練を実施しました。そこでは、地域防災計画の検証、関係機関及び協定締結団体との連携確認を行ったほか、市民の皆さまに防災に関心を持っていただきたいという思いから、一部の自治会の方々にご協力をお願いし、避難所開設訓練にご参加いただきました。
災害発生時には、市民の皆さまの安全を確保するために迅速かつ的確な判断、対応が求められます。市ではこの度の訓練での課題を踏まえ、引き続き防災力の強化に取り組む所存です。
しかしながら、皆さまの安全を確保するためには行政の力(公助)だけでなく、地域での助け合い(共助)や、一人ひとりの災害への備え(自助)が必要不可欠です。
そのためにも普段から、避難所の場所を確認しておくことや、飲料水や非常食等を備蓄すること、また家庭でも災害発生時の対応を話し合うなど、有事の際に備えていただけますと幸いです。
災害はいつ起こるかわかりません。皆さまにおかれましても、いま一度、普段からの備えをご確認いただきますようお願い申し上げます。
令和6年9月「石橋高等学校野球部夏の甲子園での活躍」
8月7日から開催された第106回全国高等学校野球選手権大会(通称、夏の甲子園)に、石橋高等学校野球部が栃木県代表として出場しました。
文武不岐を掲げる彼らは限られた時間の中で練習を行い、強豪ひしめく県予選を見事に突破しました。球児の憧れの地「阪神甲子園球場」で全国の強豪と正面からぶつかり合う、その姿は私たちに夢と感動を与えてくれました。選手、関係者の皆さまに改めて敬意を表します。
8月13日の2回戦、私も現地で応援をさせていただきました。会場には多くの生徒、卒業生、関係者の皆さまが駆けつけ、身につけたTシャツやタオルでオレンジ一色に染まったアルプススタンドから、メガホンで声援を送っていました。30℃を超える気温の中で選手とともに一丸となって汗を流す姿からは、石橋高等学校に関わる多くの皆さまの「熱さ」を強く感じ、大人たちや“まち”すらも巻き込み旋風を起こしてしまう「若い力」のすばらしさを、改めて思い知らされました。
今後もより一層、若い皆さんとの交流を大切にするとともに、その「若い力」を存分に発揮できる場を提供できるよう努め、下野市をますます盛り上げていきたいと思います。
今後も市民の皆さまとより良いまちづくりに取り組むべく、邁進いたします。
R6.8 ITパスポート取得による人材の育成
下野市では、「ITパスポート(iパス)」を市職員が取得するための全庁的な支援を始めました。
iパスは業務に必要なIT(情報技術)の知識に加えて、経営戦略、財務、法務、プロジェクトマネジメントなど、ITを利活用するすべての社会人、これから社会人となる学生が備えておくべき幅広い分野の総合的知識を問う国家試験です。
私はできる限り多くの市職員にiパスの取得に挑戦して欲しいと考えています。
そして、テクノロジーの力を行政運営に活用して市民の皆さまへの情報発信やより多くの意見の収集、医療や福祉、教育や産業等の幅広い分野の現状の把握、行政サービスのさらなる充実を実現させたい思いです。
人はそれぞれ計り知れない力を持っています。もちろん、iパスに限らず市職員にはさまざまな分野に関心をもつとともに、常に新しい知識を吸収し、自信や希望をもって職務に取り組んで欲しいと思います。
そのために、今後も引き続き市職員がやりがいを持てる環境づくりを進めることで行政サービスの向上を目指し、市民の皆さまに幸せをお届けできるよう努めてまいります。
令和6年7月「医療のまち下野の飛躍を目指して」
「今月の表紙」のとおり、下野市と自治医科大学との連携・協力に関する協定が締結されました。
市長就任当初より、自治医科大学との連携強化を切望していましたので大変嬉しく思っております。
なぜ下野市が医療のまちであるのか。それは、単に病院やクリニックが多く存在する市であるということではなく、医療や福祉、防災やまちづくり等、自治医科大学との連携・協力に根ざすものです。そして、この度の協定により医療のまちとしての取り組みを明確に発信することが可能になりました。これは、本市にとって本当に大きな意味があります。
今後も、下野市に魅力を感じてくださる方がますます増えることを期待し、そして、この度の協定締結を新たなスタート地点として捉え、「自治医科大学を柱に、将来に向かって医療都市として、どのようなまちづくりを進めていくのか」市の将来像に夢を膨らませながら、まちづくりに全力をあげて取り組んでいきます。
医療のまちとして、下野市はこれから更に大きく発展します!
令和6年6月「ドイツとの交流」
4月23日にクレーメンス・フォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使が来市され、自治医科大学や天平の花まつり会場をはじめとする市の特徴が分かる施設の視察をされました。
また、グリムの館を会場として講演会を開催するなど、市民との親交を深められ、市としても素晴らしい機会となりました。
本市とドイツとの交流は長い歴史があり、来年にはディーツヘルツタール(旧シュタインブリュッケン)と姉妹都市締結50年目を迎えます。
これまで長く本市とドイツを繋ぎ親善を図ることにご尽力をくださいました皆さまに、心から敬意を表します。
これからもより一層関係を深めつつ、ドイツの魅力を下野市のシティプロモーション等に活かせるよう取り組みたいと考えております。
さらに、ドイツをテーマとしたイベントの開催も考えており、友好関係のさらなる進展に努めていきます。
令和6年5月 「明日香村と東の飛鳥」
3月22日、飛鳥時代の宮殿や史跡が多く発掘されている奈良県明日香村を訪問しました。同村との交流を深めて、2年後の市政20周年を期に友好都市などの協定を結ぶことが目的です。
下野市にも、貴重な史跡などが数多く存在しています。古代から人が集まり住むのに「ウッテツケ」であったからだと思います。明日香村をはじめ、関連する自治体との親交を積極的に深めながら、下野薬師寺跡や下野国分寺跡などの文化財を活用した「東の飛鳥」プロジェクトの推進を図り、下野市のブランド力の向上に努めていきます。
令和6年4月
下野市は自然災害の少なく、平坦で安定した地域であり、安全で住み良いまちといえます。しかし、今年の元日に発生した能登半島地震を受け、災害はいつ何時起こるか分からないことを改めて考えさせられました。今回の震災において、被災地における災害復旧復興を支援するため、下野市からはこれまでに応急給水活動や住家被害認定調査のほか、避難所の運営や避難所における健康支援業務に従事するため、保健師を含む合計20名以上の職員を派遣いたしました。一日も早い被災地の暮らしの回復をお祈りしますとともに、今後も被災地に寄り添いながら、状況に応じ必要な支援に取り組んでまいります。
想定外の事態に対応するには、日常からの備えが重要です。改めて災害への備えを再確認するとともに、有事の際には(もちろんないことを祈りますが)被害を最小限に留め、市民の皆さまの安全を守るためにも、今回の被災地への派遣で得られた経験を生かし、行政、地域、関係機関などと連携し、より一層、防災対策と危機管理体制の強化に取り組んでまいります。