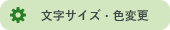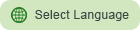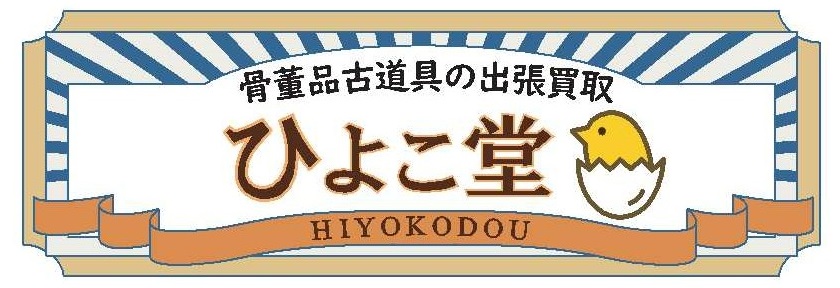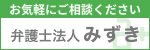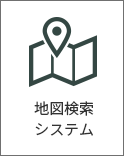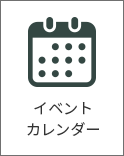「東の飛鳥」~下野市の歴史・文化的特性~
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
「東の飛鳥」とは
下野市は、はるか昔から穏やかな気候に恵まれたとても住みやすい場所であったため、多くの人々が暮らしてきました。
悠久の歴史の中で多くの人々が暮らしてきた証は、数多くの文化財として、今日に継承されています。
その中でも特筆すべきことは、古墳時代から飛鳥・奈良時代にかけて東国(東日本)を代表する史跡などが市内に多数所在していることです。
飛鳥時代の変遷を表す重要な史跡が集中するという歴史的特性は、日本という国が成立したときに都が置かれた古代文化発祥の地である奈良県飛鳥地方と共通しています。
下野市の歴史的特性をわかりやすくお伝えするために、「東の飛鳥(ひがしのあすか)」と名付けました。
動画でひも解く「東の飛鳥」誕生秘話
東の飛鳥のシンボルマーク(商標登録第6144912号)

このシンボルマークは、東国の古代史を解明するために重要な史跡や文化財が多数保存・継承されてきた「東の飛鳥」である下野市をイメージしたものです。
詳細は、「東の飛鳥」のシンボルマークについてをご覧ください。
「東の飛鳥」下野市域の歴史と史跡
今から千数百年前、アジアの東端の小さな国の仕組みが大きく変化し、日本という国が生まれました。巨大古墳に代表されるシンボリックな政治の仕組みから、中央と地方が一体となって機能するための政治・行政組織が各地に整備されました。
その流れの中で、当時、東国の中でも決して先進地ではなかったこの小さな下野市域が重要視され、政治・文化中心地となった奈良県飛鳥地方から様々な情報や人やモノがこの地にもたらされ、東国北部の政治や文化の先進地として繁栄しました。
下野市域には400か所以上の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)や史跡が残されています。中でも古墳時代以降、飛鳥・奈良・平安時代の遺跡が多く、この時代に東国(東日本)の中でも当地域が飛鳥・奈良に置かれた中央政権から重要視され、発展を続けたことが理解できます。
この時代の下野市域の歴史を追いながら、代表的な史跡をご紹介します。
6~7世紀
下野市域には12,000年前の旧石器時代から人々が居住した痕跡があり、古墳時代には有力な豪族が現れました。
しもつけ古墳群は、栃木県南部(下野市・栃木市・小山市・上三川町・壬生町)の各地に所在する大型の古墳群です。古墳時代後期(6~7世紀)に、この地域を支配した下毛野氏(しもつけのうじ)の一族によって造られました。
市内には、「下野型古墳」と呼ばれる甲塚古墳(かぶとづかこふん)、御鷲山古墳(おわしやまこふん)、三王山古墳(さんのうやまこふん)、横塚古墳などが造られました。
|
御鷲山古墳と円筒朝顔形埴輪(再現イメージ) |
甲塚古墳の人形埴輪(再現イメージ) |
7世紀末以降
飛鳥時代末、東国最大級の古代寺院・下野薬師寺(しもつけやくしじ)が建立されます。天武天皇の信任を受けて大宝律令の選定を行うなど中央政界で活躍した下毛野朝臣古麻呂(しもつけのあそんこまろ)の関与によって、関係の深い地とされる現在の下野市薬師寺付近が建設地に選ばれました。
奈良時代前半には東国唯一の国立寺院として造営が進められ、奈良時代後半には、東大寺(奈良県)や筑紫観世音寺(福岡県)とともに、日本三戒壇の一つである戒壇(かいだん・僧の養成所)が置かれました。下野薬師寺で受戒した僧は、東国各地の国分寺などに派遣されました。
東国における国の仏教政策の中心的な役割を果たした下野薬師寺の姿は、都の壮大な寺院のようであったと伝えられています。
現在は、これまでに行われた発掘調査の成果をもとに史跡公園として整備が行われています。
多くの謎に包まれた下野薬師寺跡の調査成果は、下野薬師寺歴史館で見学することができます。
|
回廊と中門(再現イメージ) |
復元回廊と梅の花 |
8世紀中頃
8世紀には、下野国分寺・国分尼寺(しもつけこくぶんじ・こくぶにじ)が建立され、古代下野国の仏教文化の中心地として栄えました。
聖武天皇は、度重なる災害や疫病によって荒廃した国の救済を仏教に求め、天平13年(741年)に国分寺建立の詔(みことのり)により、全国に良い場所を選んで国分寺と国分尼寺を建てるよう命じます。下野市域は古来より高低差があまりなく、開けていて安定した自然災害の少ない地域であったため、建立の地に選ばれました。下野国分寺・国分尼寺では、国家の平和を祈るための儀式が執り行われました。
現在は、これまでに行われた発掘調査の成果をもとに史跡公園として整備が行われています。
下野国分寺跡・国分尼寺跡の調査成果は、しもつけ風土記の丘資料館で見学することができます。
|
下野国分寺の金堂と回廊(再現イメージ) |
下野国分尼寺跡と桜(天平の丘公園内) |
「東の飛鳥」を知ろう!
しもつけ風土記の丘資料館や下野薬師寺歴史館では、「東の飛鳥」の重要な史跡や文化財について知ることができるイベントを企画しています。
楽しみながら「東の飛鳥」の歴史に触れてみませんか?
| 開催時期 | イベント内容 |
|---|---|
| 春 |
|
| 夏 |
|
| 秋 |
|
| 冬 |
|
そのほか、各種講演会や発掘現場現地説明会、小・義務教育学校でのふるさと学習などを実施しています。
開催に関する情報は、歴史・文化のページでお知らせします。
「シモツケ くらし ウッテツケ」
~歴史が証明するくらしやすさ~

「シモツケ くらし ウッテツケ」は、東の飛鳥・下野市の歴史的特性により証明されている「くらしやすさ」をPRするためのキャッチコピーです。
詳細は、シティプロモーションキャッチコピー「シモツケ くらし ウッテツケ」をご覧ください。