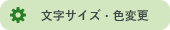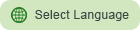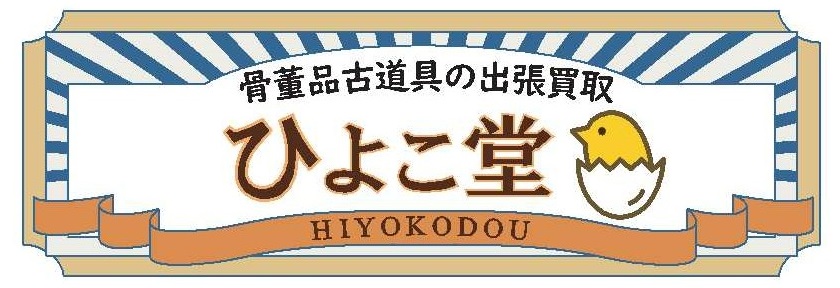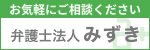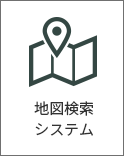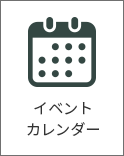ナラ枯れ被害について
ナラ枯れとは?
ナラ枯れとは、カシノナガキクイムシ(以下カシナガ)という、体長5mmほどの虫が原因で
引き起こされる樹木が枯死してしまう病害です。
カシナガ自身が病原菌を保有しており、ナラ類の樹木に入り込んで樹幹内を食害していく過程で、この病原菌が原因となり樹木が枯死してしまうのです。
夏などでも葉が赤く紅葉のように枯れてしまい、根元部分には食害する際に出るフラス(木くずと糞が混ざったもの)が大量に発見されるのが特徴です。
なぜ防除が必要なのか
ナラ枯れを放っておくと被害が爆発的に増えてしまい、景観の悪化、森林機能の低下、森林価値の低下等が懸念されます。
例)青森県H28:23本(被害木)⇒H29:354本⇒H30:1,103本
わずか2年間で約48倍、被害木が増加してしまった事例もあります。そのため、被害を抑えるためには早期の防除が重要になってきます。
防除するには
カシナガの活動時期は6月から始まり、8~9月付近で食害が起こり2週間ほどで急激に枯死します。
そのため、被害木を発見したら次の年の5月までに防除を行う必要があります。被害木の防除方法はさまざまですが、一番効果的なのは被害木を伐採し、伐採後の樹木を薬剤燻蒸若しくは焼却する方法です。
掲載日 令和6年8月20日
更新日 令和6年12月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)